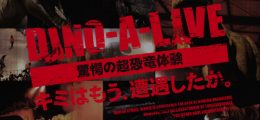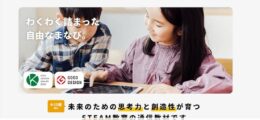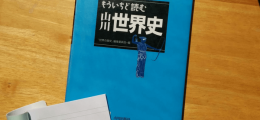子供におもちゃを買うなら、もはやSTEM玩具一択!?
そんなレベルで売れ筋&絶好調なアメリカのSTEM界隈。
⇒ Amazon、科学おもちゃの定期購入サービスを開始 | TechCrunch Japan
先の年末セールでは、Amazonの数あるカテゴリー内で、来訪者数第2位、売上ではなんと1位を記録。
あれだけの商品がありながら、クリスマスシーズンとはいえ売上トップになるとは、アメリカのSTEM熱は相当なものです。
スポンサードリンク
月2296円、対象年齢(3コース)を選んで、あとは届くのを待つだけ
そんな中、昨日リリースしたのが、そのSTEM玩具を対象年齢に合わせ毎月送ってくれる定期購入サービス「STEM Club」です。
月額は19.99ドルと、日本円にして約2,296円(執筆時)。
対象は「3~4歳」「5~7歳」「8~13歳」に区分され、最近リリースされたばかりの製品やAmazonが独自に扱っているSTEM玩具が送られてくるそうな。
欲しい商品を選べるわけではありませんが、偶然送られてきた玩具が子供の新たな一面を発掘してくれそうなプログラムです。
日本でも、以前から通信教育の付録に知育玩具はありますが、おまけではなく玩具が主役として成り立つ点はさすがSTEM先進国。

特にAmazonでは、一昨年から既にSTEM玩具を専門に扱う「STEM Toys & Games Store」を開設していたこともあり、サービスに対する需要をしっかり受け止めての展開となっています。
残念ながら、「STEM Club」「STEM Toys & Games Store」共に、アメリカ限定のサービスとなっているため、日本での展開は見込まれていません。
STEMに対する関心の高まりが、しっかりと実売につながってくればといったところでしょうか。
最近やっと国内でも、プログラミング教室が通わせたい習い事第1位になったこともあり、日本ではようやくその土壌が整ってきたといった状況です。
【関連】
・プログラミング教室への関心ついでに知っておきたい無料の子供向けオンライン教材6つ
休刊が非常に惜しい、元祖STEM玩具を提供していた「学研の科学の本」
こうした教育系の定期購入サービス(サブスクリプションサービス)は、一般的に通信教育のイメージが強いかもしれません。
実際、国内ではそもそも市場が大きくなかったため、一部の大手が関連事業として手がけてきました。
有名所は進研ゼミ(不定期)や、「学研の科学の本」あたり。

特に学研は、子供の頃おもちゃ代わりに充てがわれた方も多かったのではないでしょうか。
そういった記憶がなくとも、家の中を見回したり押し入れを整理すると、それっぽい玩具が出てくることもちらほら。

ちなみに現在、HPにある科学のふろくギャラリーというページから、これまでに提供されてきた元祖STEM玩具(実験・観察教材)が一覧できるようになっています。
眺めてみると、どこかで見たことのある代物や玩具が、実は学研のものだったと今になり再発見できると思います。
それにしても、1963年から2010年までの間に開発されてきた玩具のバリエーションはさすがです。
過去作品をもとに、今の時代に合わせたリメイク版がいくらでも出せそうなほどクオリティは高く、休刊してしまったのが本当に惜しいコンテンツでした。
それでも、今は3Dプリンタの低価格化や「DMM.make AKIBA」といったモノづくり施設の拡充も進み、個人でもハード作りが可能な環境が整ってきています。
既存の教育関連企業だけでなく、個人や小規模メーカーが新たな知育・STEM玩具プレイヤーとして登場することが待たれます。
日本で展開中の知育玩具”レンタル”サービス「Toysub(トイサブ)」

その他、STEM玩具ではありませんが、知育玩具を定期的に利用できるレンタルサービスもあります。
こちら、株式会社トラーナ(旧トラーナコントロールズ合同会社)運営の「Tuysub(トイサブ)」では、未就学児(0歳3ヶ月〜3歳)のいる家庭を対象に、600種類以上の知育玩具・おもちゃのレンタルをしています。
成長に合わせて逐一お金をかけられない、どんな玩具で遊ばせていいのかわからない、おもちゃが増え家にスペースが無くなって困っている。などなど
子育てや幼児教育に悩みを抱えるご家庭で、非常に使い勝手の良いサービスではないかと。
紙やデジタル教材だけでなく、実際に触れて遊べる知育玩具の重要性や、おもちゃの膨大な廃棄量に着目し、バランスのよい学習体験をシェアリングエコノミーで解決することを掲げています。
非常に共感できるコンセプトですし、ぜひとも日本中に広まって欲しい取り組みです。
現実世界のなんで?どゆこと?を喚起する、最上のコンテンツ
紙教材でもデジタル空間でもない、現実世界だからこそ得られるフィードバックは、子供にとってなによりも強烈な体験です。
文字で読む、動画で観ることが手軽にできるようになった今でさえ、顕微鏡で見るミクロな世界や初めて火や薬品を扱う緊張感は、強く印象に残る出来事かと思います。
字面や画面越しでなく、現実に目の前で起こっていることのインパクトは、興味関心やさらなる探究に拍車をかけること請け合いです。
多様な学習体験の一翼を担う知育(STEM)玩具は、ぜひ注目すべきカテゴリーとして今後も取り上げていければと思います。
【関連】
・遊んで伸ばす創造性と問題解決力。世界中で話題の「スマートトイ」を悩んで4つあげてみる